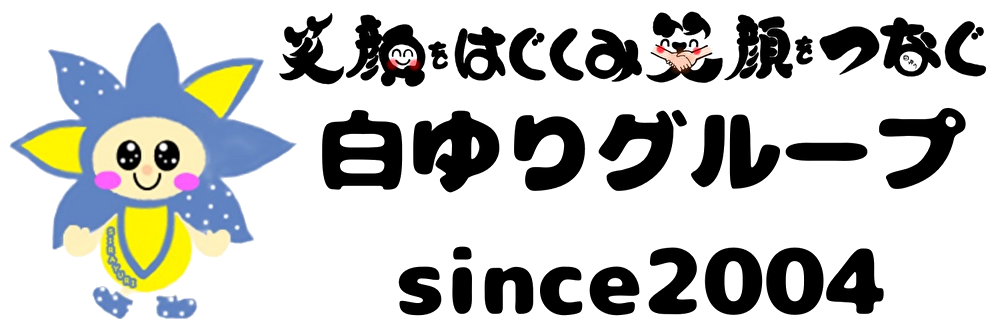消火訓練 チャレンジハウスHERO
もしもに備える。HEROでの消防訓練の一日
新しい季節を迎えて、防災意識も改めて見つめ直したい時期。
先日、チャレンジハウスHEROでは地元消防署の皆さまをお迎えし、実際に消火器の使い方実践や、火災時の避難誘導の仕方を体験する訓練を行いました。
普段は穏やかな日常を過ごす子どもたちやスタッフにとって、「火災」という緊張感のある状況を体験することは、感覚として“備える力”を育てる大切な機会となりました。
なぜ訓練が必要なのか:備えなければならない「見えないリスク」
火災はいつ、どこで起こるか予測が難しく、初期対応が遅れると大きな被害につながります。
普段意識しにくいけれど、
煙の広がる速さ
避難経路が目視できない状態
初期消火のタイミング
こうした“見えないリスク”に備えるには、実地での“動き”を体験しておくことが強みになります。
また、子どもたち自身が「自分も動く人」になっておくことで、非常時に恐怖や迷いを減らす効果も期待できます。
訓練で体験したこと:消火器・避難誘導・119通報
- 消火器の使い方講習(消防署員による指導付き)
まず、消防署の方から消火器の基本操作方法をレクチャーしてもらいました。
「ピンを抜く → ノズルを火元へ向ける → レバーを押す」という一連の動作は、よく「ピン・ポン・パン」の合言葉で教えられることが多い方法です。
その後、実際に訓練用の水消火器を使って“火元に見立てた的”へ放水を行い、操作感をつかむ体験をしました。
初めて手にする子も多く、「思ったより重い」「レバーを押す力加減が難しい」と声があがりつつ、一人ひとり順番に体験しました。
- 避難誘導訓練(火災発生時シミュレーション)
次に、「火災発生」の想定で、施設内から外への安全な避難ルートを確認しながら誘導訓練を行いました。
煙の出やすい場所を想定して見えにくくしたり、非常口までのルートを再確認するなど、緊張も伴う訓練です。
また、スタッフと子どもたちの連携を確認し、逃げ遅れがないか人数把握をする場面も取り入れました。
- 119通報訓練(模擬通報)
火災時にまず行うべき「119番通報」も訓練に含まれます。消防署とやりとりする想定で、
出火場所
自分の名前・電話番号
被害状況(火元・気になるものの有無)
などを伝える練習をしました。これにより、いざという時に緊張していても言葉が出せるようになる訓練効果があります。
実際に参加して感じた変化・学び
子どもたちの表情にも緊張感が走り、訓練後には「火事って怖いな」「でも少し安心できる動きも覚えた」という声も聞かれました。
スタッフ間でも「消火器を使うときの姿勢」「避難誘導のタイミング」について振り返りをして、より安全な手順・補助具の配置を検討する契機になりました。
消防署の方からは、普段使わない設備(避難はしご、非常口の表示など)への注意喚起もあり、施設の安全強化に結びつく指摘もいただけました。
こうした訓練を通じて、「いざという時に躊躇しない行動力」を、子ども・スタッフともに“体で覚える”ことの大切さを改めて実感できました。
地域に伝えたいメッセージ:訓練は“やって終わり”じゃない
消防訓練は一度やって終わりではなく、継続性・振り返り・改善が肝心です。
訓練後には、時間のかかった場所や誘導で迷った箇所などをスタッフで共有
消火器の設置場所・交換期限の確認
非常口・避難経路の表示(照明・誘導灯など)の再チェック
定期的な訓練スケジュールの見直し
こうしたアクションを重ねることで、防災力は少しずつ底上げされます。
また、地域や保護者の皆さまにも「知ってほしいこと」を伝えられる機会にもなりますので、訓練に立ち会っていただいたり、報告を共有することも大きな意味を持ちます。
訓練の成果を未来につなげるために
この日の消防訓練を通じて、チャレンジハウスHEROでは「安心できる場づくり」の一環として、さらなる安全対策を進めています。
いざという時、「慌てないで動ける力」は、日ごろの備えから育まれます。今回の訓練をきっかけに、スタッフも子どもたちも少しずつ防災意識を高めていけたらと願っています。
「まずはお気軽にご相談ください」
チャレンジハウスHEROでは、療育活動とともに、安全・安心な支援環境づくりにも力を入れています。
消防訓練や安全対策などに関して、見学時に実際の様子をご案内できますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ: 06‑6770‑5584
スタッフ一同、心よりお待ちしております😊