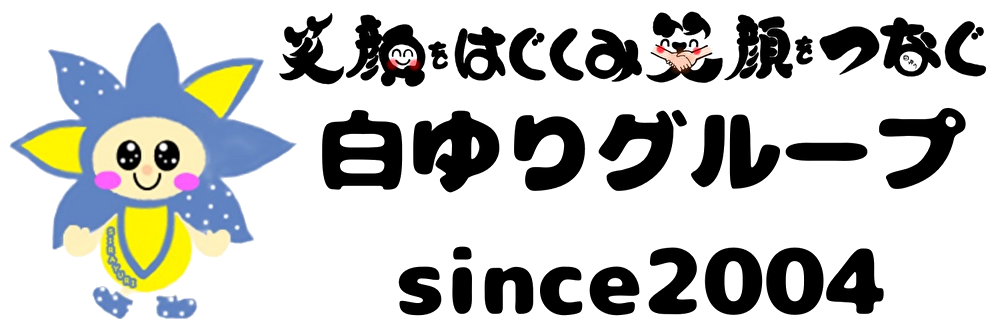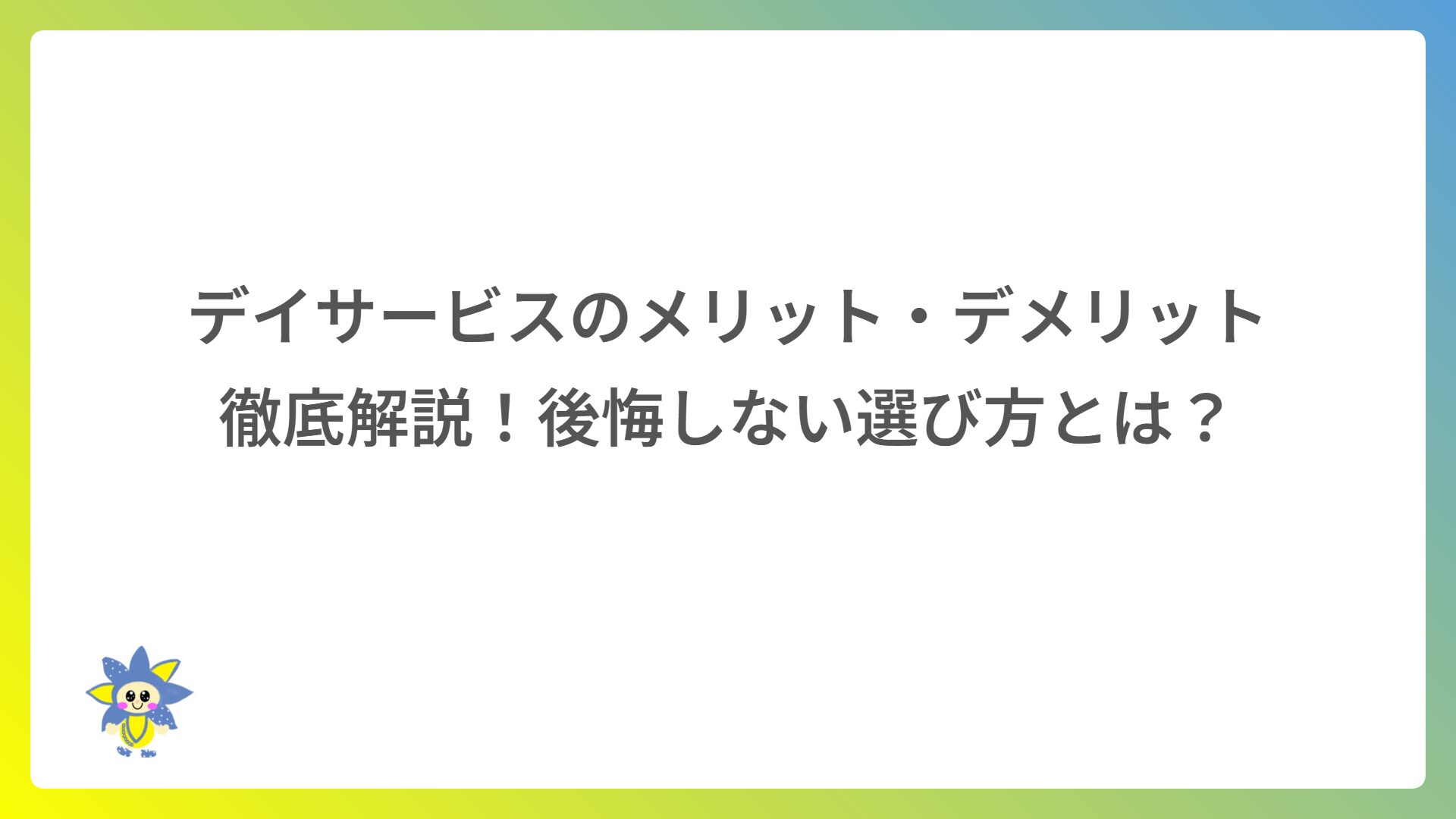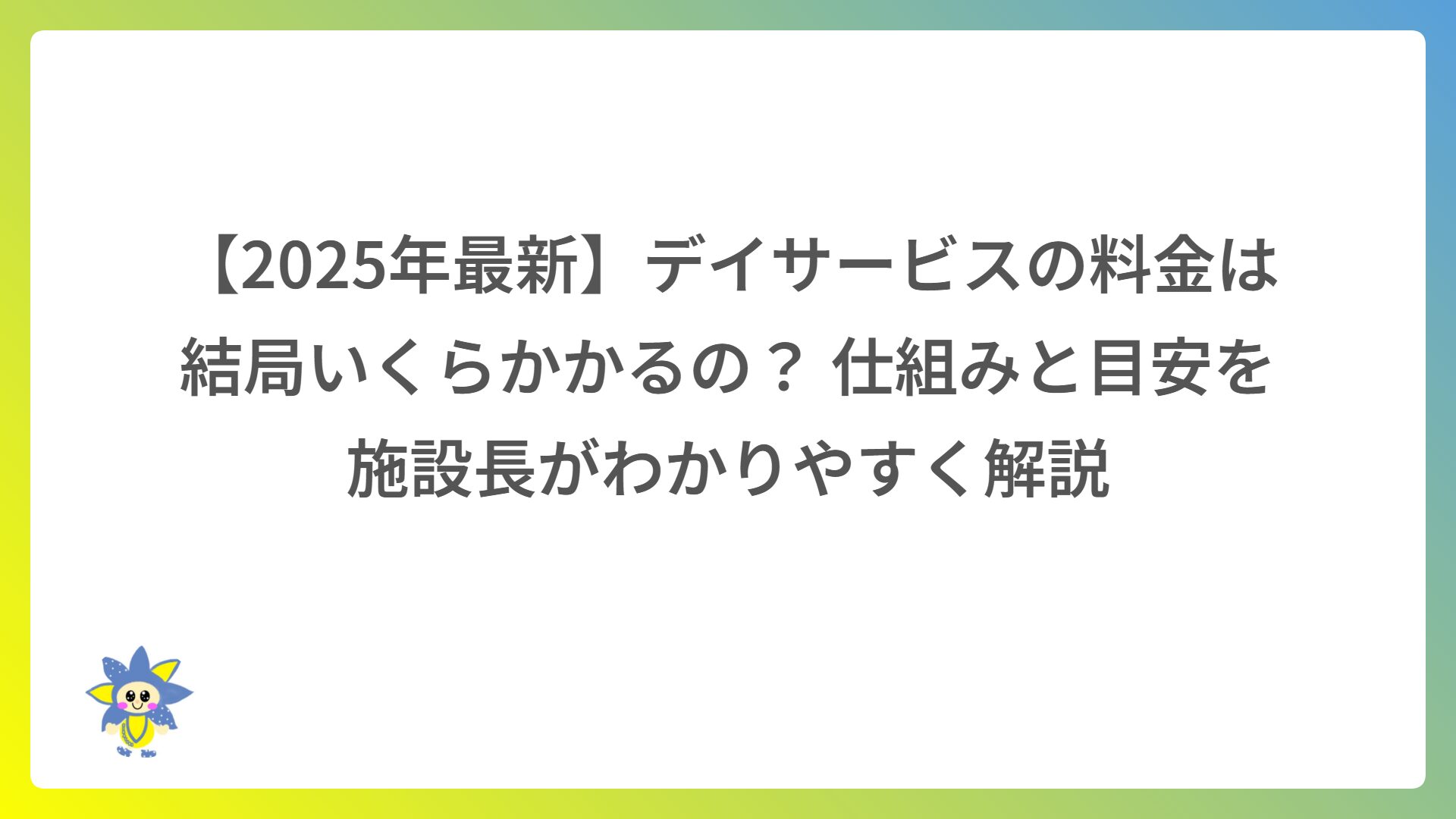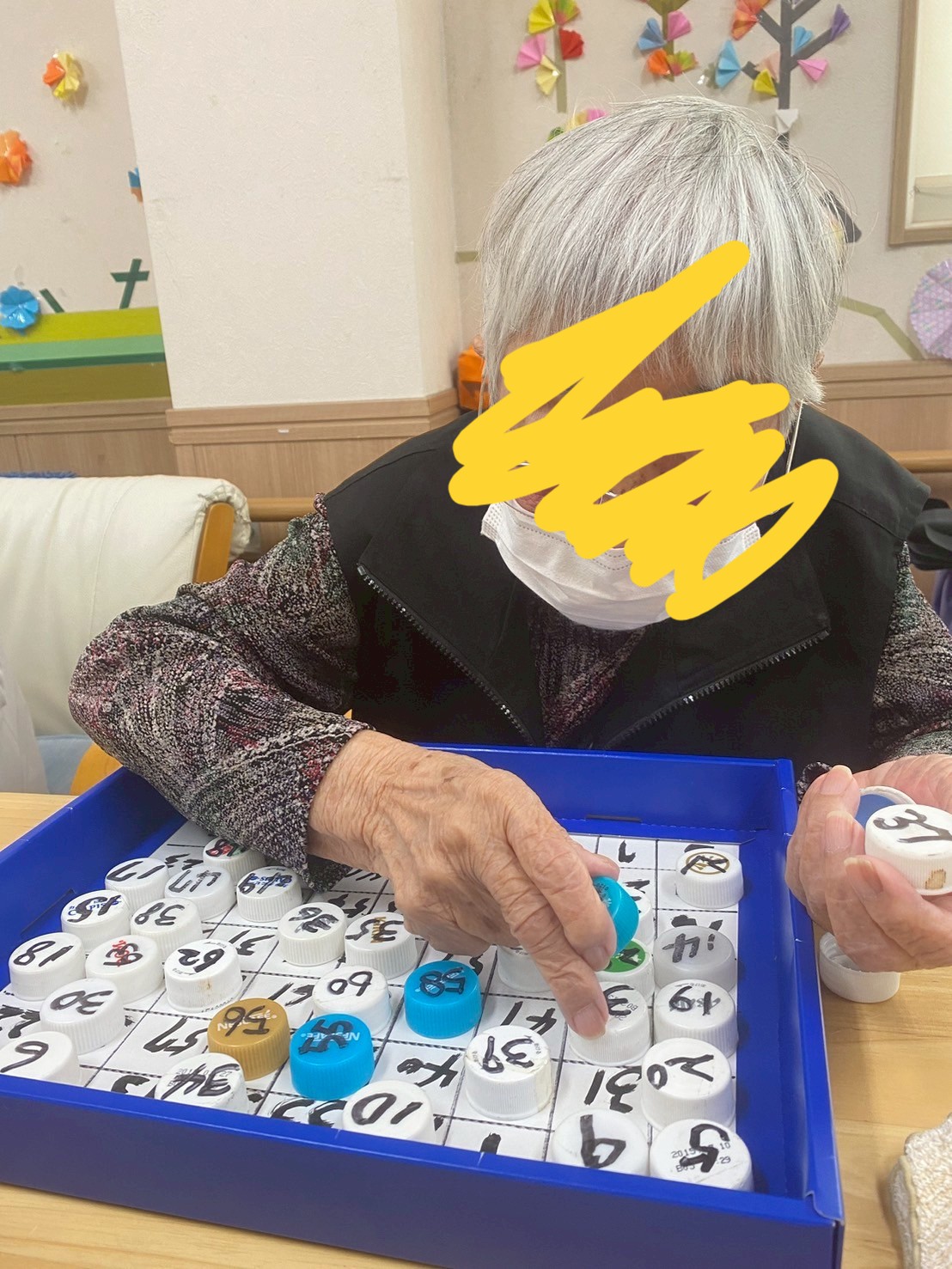【論文解説】高齢者の転倒予防:久留米大学の研究が示す「足把持力」と「注意機能」の重要性
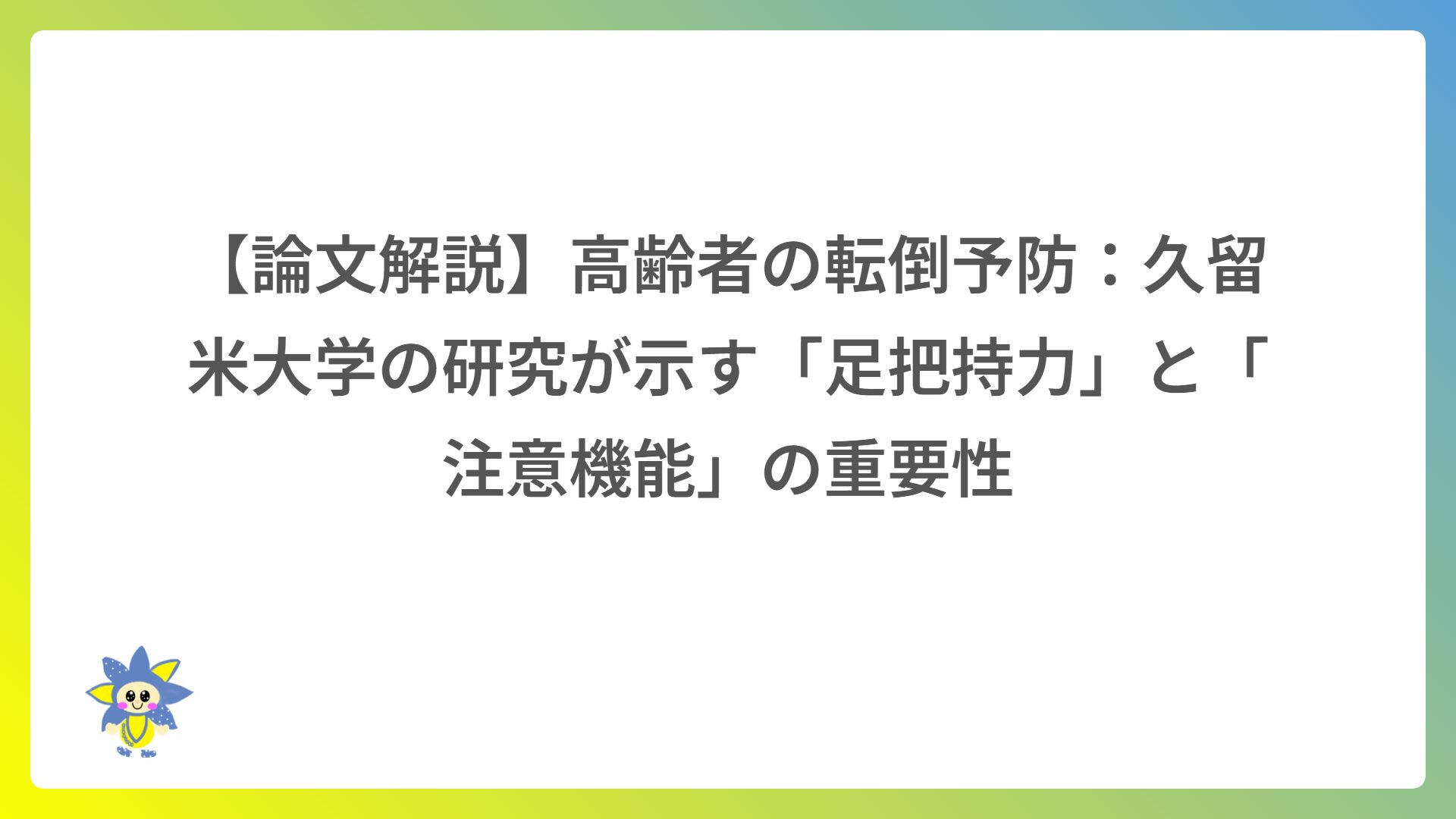
なぜ今、高齢者の転倒予防が重要なのか
日本は世界でも類を見ない速さで高齢化が進行しています 。
それに伴い、高齢者の「寝たきり」は介護保険制度においても大きな課題となっています 。
高齢者が寝たきりになる原因は様々ですが、「脳卒中」に次いで多いのが「老衰」「骨折・転倒」です 。
特に転倒による大腿骨頸部骨折などは、生活の質(QOL)を著しく低下させ、そのまま寝たきり状態につながりやすい重大な問題です 。
この「転倒」をいかに予防するかは、福祉・医療分野における急務の課題と言えます 。
この記事では、高齢者の転倒予防に関して重要な示唆を与える、久留米大学の研究報告(村田 伸 氏、津田 彰 氏ら) の内容について、その核心部分を解説します。

久留米大学の研究が着目した「転倒」の2大要因
この研究(『高齢者の転倒予防に関する研究』久留米大学心理学研究 2006, No.5) は、従来の転倒予防策が「身体機能の向上訓練に偏っている」 と問題提起しています。
一般的に転倒予防といえば、下肢筋力(太ももを上げる筋力など)のトレーニングが重視されがちです 。
しかし、研究者らは、それだけでは不十分であり、転倒には「身体的要因」と「精神運動・認知的要因」の両方が関与していると指摘します 。
この研究では、在宅の障害高齢者を対象とした実験的フィールド研究に基づき、以下の2つの要因が転倒の重要な予測因子であることを実証しました 。
- 身体的要因:足把持力(そくはじりょく)
- 精神運動・認知的要因:注意機能
要因1:身体的要因としての「足把持力」とは?
「つまずく」こと自体を防ぐため、下肢を振り上げる筋力(大腿四頭筋など)が注目されがちです 。しかし、研究者らは「振り上げた足や身体を支えるもう一方の足(支持脚)の重要性」 に着目しました。
そこで定義されたのが**「足把持力(そくはじりょく・あしはじりょく)」です。
これは、「足指と足底で地面をしっかりとつかむ力」**を指します 。
ヒトの歩行時、足は地面と身体が唯一接する場所であり、バランスを保つためのセンサー(足底の感覚入力) としても、身体を支える土台としても機能します。
この「地面をつかむ力」が弱まれば、立位姿勢そのものが不安定になります。
研究では、この足把持力を測定し、他の動作能力との関係を分析しました。
その結果、以下の明確な相関関係が確認されました 。
- 足把持力が強いほど、片足で立っていられる時間(片足立ち保持時間)が延長する 。
- 足把持力が強いほど、歩く速度(歩行速度)が増加する 。
- 足把持力が強いほど、立っている時のふらつき(重心動揺)が減少する 。
さらに、足把持力の低下が転倒の重要な危険因子であることが統計的に示されました 。
加えて、3ヶ月間の「足把持力トレーニング」を実施した介入研究では、トレーニングを行ったグループにおいて足把持力の向上と転倒予防効果(転倒者比率の有意な減少)が確認されました 。
このことは、足把持力が単なる指標ではなく、訓練によって改善可能であり、転倒予防に直結することを示しています。

要因2:精神運動・認知的要因としての「注意機能」
転倒は、足がもつれるといった身体的な問題だけで起こるわけではありません。
研究では、精神運動・認知的要因、特に**「注意機能」**の低下が転倒を引き起こす重大な予測因子であることも実証しています 。
高齢者の転倒は、「他に気を取られた」「段差に気づかなかった」など、周囲の環境に対する注意力の低下によって引き起こされるケースが多いことが指摘されています 。
研究者らは、この「注意機能」を客観的・定量的に評価するため、**「Trail making test Part A (TMT-A)」**という検査を用いました 。
これは、ランダムに配置された数字を順番に線で結んでいく作業の速さを測るテストで、視覚的な注意機能や処理速度を評価するために広く用いられています 。
研究では、在宅障害高齢者を対象にこのTMT-Aを実施し、その後の1年間の転倒発生を追跡する「前向き研究」を行いました 。
その結果、ベースライン(研究開始時)のTMT-Aの成績が低い(=注意機能が低下している)人ほど、その後の1年間で転倒しやすいことが統計的に実証されました 。
これは、「注意力の低下」が、足把持力の低下 や足関節の可動域制限 と並んで、将来の転倒を予測する重大な因子であることを強く示唆しています 。
研究が示す今後の展望:総合的な予防対策の必要性
この久留米大学の研究報告 は、高齢者の転倒予防のあり方について重要な提言をしています。
転倒予防は、身体機能の向上訓練だけに偏ってはならない、ということです 。
転倒が「足把持力」のような身体的要因と、「注意機能」のような認知的要因の両方によって引き起こされる「予測可能な事象」である以上 、アプローチも両面から行う必要があります。
研究者らは、今後の課題として、以下のような「総合的かつ効果的な転倒予防対策」の体系化が必要であると結論づけています 。
- 身体機能の向上訓練(足把持力トレーニングなど)
- 心理学的アプローチ(注意力トレーニングなど)
私たち福祉・介護の現場においても、単に「筋力を鍛えましょう」と呼びかけるだけでなく、利用者様が周囲の環境に意識を向ける(注意する)ことを促すような認知的なアプローチや、ストレス管理といった心理的なケアも同時に行う、総合的な視点を持つことが求められます 。

まとめ
今回は、久留米大学心理学研究科・文学部心理学科による、高齢者の転倒予防に関する研究報告 を解説しました。
- 研究の背景: 急速な高齢化に伴い、寝たきりに繋がる高齢者の転倒予防は急務の課題である 。
- 身体的要因: 「足把持力(地面をつかむ力)」の低下が転倒の危険因子であり、トレーニングにより改善可能である 。
- 認知的要因: 「注意機能(TMT-Aで評価)」の低下も、転倒の重大な予測因子である 。
- 今後の展望: 従来の身体訓練だけでなく、注意力トレーニングといった心理学的アプローチを加味した**「総合的な予防対策」**の体系化が必要である 。
この研究は、高齢者の転倒を多角的に捉え、身体と認知の両面からのアプローチの重要性を示した、非常に価値のある報告です。
大阪市平野区で「総合的な転倒予防」をご検討の方へ
白ゆりグループでは、今回ご紹介した久留米大学の研究報告(Murata & Tsuda, 2006)にあるような、身体機能と認知機能の両面からアプローチする「総合的な転倒予防」の視点を大切にしています。
私たちの日中の活動プログラムでは、単に筋力向上を目指すだけでなく、利用者様一人ひとりの「注意機能」や「地面を捉える力(足把持力)」にも着目した個別支援を心がけています。
- 「最近、家族の足元がふらついて心配…」
- 「転倒を予防するために、専門的なサポートを受けさせたい」
- 「日中の活動を通じて、転倒しにくい身体づくりや、認知機能の維持・向上を目指したい」
大阪市平野区を拠点に、こうしたお悩みやご要望に対し、経験豊富なスタッフが親身になってお応えします。
ご本人様やご家族様はもちろん、ケアマネジャー様からのご相談も随時受け付けております。
施設の見学や無料相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
参考文献
Murata, S., & Tsuda, A. (2006). 高齢者の転倒予防に関する研究. 久留米大学心理学研究, (5), 91-104.