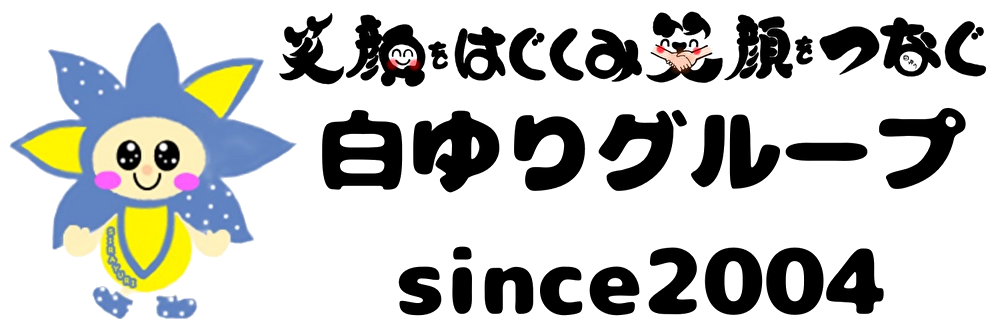餃子の皮でピザづくり🍕【ぐりーてぃんぐ】
食べることは毎日のこと。けれど、野菜がちょっぴりニガテだったり、包丁を前にすると手が止まったり…そんな“あるある”は、就学前後のお子さまにとって自然な姿です。
とはいえ将来の自立を考えると、「切る・のせる・待つ・片づける」までの一連の流れを、安心して経験できる場は早めに用意したいところ。ご家庭だけで頑張るのは、時間も心もなかなか大変です。
そこで、コミュニケーション育成型児童デイぐりーてぃんぐ(大阪市東住吉区)では、調理実習で「ピザづくり」に挑戦しました。工程を見える化し、役割を細かく分け、成功の階段を一段ずつ。

最初は包丁にドキドキだった子も、両手の位置を確認しながら“ネコの手”でトントン。焼き上がったピザをほおばるころには、「ピーマンいけた!」という誇らしい笑顔が広がりました。
焼き色がつくのをタイマーで“待つ”経験は、衝動をコントロールする練習にもなります。完成後は「ありがとう」「どうぞ」のやりとり。味わうのはピザだけじゃない、自分でできた達成感です。

そして、こうした小さな成功体験の積み重ねが、食の幅・手先の協調・コミュニケーションの土台を、やさしく強く育てていきます。
見学や体験のご相談は、この記事の最後にご案内しています。ぜひお気軽にどうぞ。
なぜ「調理実習」?—結論から言うと、生活力と対人スキルの両方が伸びるから
結論:ピザづくりのような調理活動は、生活動作の自立とコミュニケーション力を同時に伸ばす最短コースです。
理由:工程が「準備→加工→加熱→盛り付け→ふり返り」と明確で、協力・順番待ち・安全配慮・道具操作といった学びが自然に盛り込めるから。
具体例:今回の活動では、次の工夫を取り入れました。
- 安全第一の下ごしらえ
・包丁前に「手袋+まな板すべり止め」/ピザカッターは両手で持つルール
・“ネコの手”を写真カードで視覚提示、スタッフと手添え→見守りの段階づけ - 見える化でドキドキを小さく
・工程ボード(イラスト):切る→ソース→具をのせる→チーズ→焼く→片づけ
・キッチンタイマーで待つ時間を数値化。残り時間が分かると落ち着けます - 役割分担で関わりを増やす
・「切る係/ソース係/トッピング係/オーブン番」
・交代制で**“やりたい”と“譲る”**の練習。言葉が出にくい子には“指差しカード” - 感覚にやさしい配慮
・ピーマンなど青み野菜は薄切り→軽く下ゆでで青臭さを軽減
・触感が苦手な子には、トング・スプーン等道具のバリエーションを用意 - ふり返りで定着
・完成後に「できた・がんばった」をシールで可視化
・写真つきふり返りシートで、ご家庭にも成功体験を共有
再結論:調理実習は、「安全・見える化・役割」の三本柱で設計すれば、楽しいが学びに変わる確かな機会になります。
子どもたちの“変化”ダイジェスト📸
- 包丁はスタッフと一緒に1本を持っていた子が、2回目には自分でリズム良くトントン。
- いつもピーマンを避けがちだった子が、「自分で切ったから食べてみる」とひと口成功。
- 焼き上がりを待つ間、タイマーと“順番カード”で席を立たずに最後まで参加。
- 配膳のときに「どうぞ」「ありがとう」が自然に出て、やりとりの回数が増加。
こうしたミクロな成長は、次の活動(買い物学習、片づけ、弁当づくり)にも波及します。成功体験は連鎖するのが良いところです。
ご家庭でもできる“安全×楽しい”ひと工夫
- 野菜は細長いスティック状に切ると押さえやすい
- 皮むきやトッピングなど、刃物を使わない工程からスタート
- タイマーや工程カードで待つ・順番を理解
- 苦手食材は「自分でのせた量だけ食べる」約束にして達成感を優先
無理なく、できた喜びを先に積み上げるのがコツです