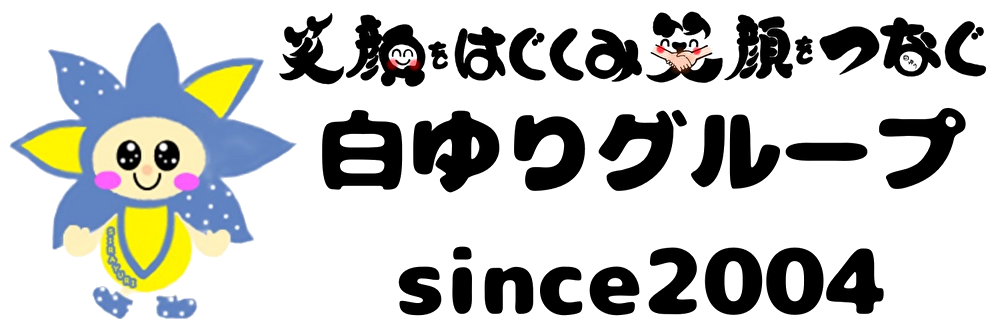科学っておもしろい!レモンと紫芋で色が変わるゼリー作りに挑戦しました!【ぽぷらの樹東住吉】

見える・触れる・驚く!色が変わるゼリー作りで育む“感覚の芽”
「これ、本当に色が変わるの?」「やってみたい!」
そんなワクワクした声とともに始まった、ぽぷらの樹東住吉での“色が変わるゼリー作り”――。

この日は、普段の運動療育とはひと味違う“科学実験のような”活動を通して、子どもたち一人ひとりが五感をたっぷりと使い、目で見て、手で触れて、味わって、たくさんの「不思議」と「できた!」を体験しました。
ゼリー液が透明から紫、そしてレモン果汁を加えることでさらに鮮やかなピンクや赤紫に変わっていく様子は、子どもたちにとってまるで魔法のよう。
「見て!変わったよ!」「なんでこんな色になるの?」と、自然と会話が生まれ、スタッフも一緒になってその驚きを分かち合いました。
活動の途中では、「レモン入れたら変わった!」「次は何色になるのかな?」といった子どもたち自身の“問い”や“気づき”がどんどんあふれてきて、活動全体がまるでひとつの「学びの探検」のような空気に包まれていました。
こうした体験は、ただ楽しいだけではありません。
触る、混ぜる、匂いをかぐ、見比べる、味わう――。
五感を通じて“変化”を実感することで、脳への多角的な刺激が入り、感覚統合を自然なかたちで促すことができるのです。
また、自分で作ったゼリーがちゃんと固まり、きれいな色に変わり、おいしく食べられるという成功体験は、子どもたちの「やればできた」「またやりたい!」という自信につながっていきます。
なぜ「色が変わるゼリー作り」を取り入れたのか?
子どもたちの発達支援において、こうした“感覚遊び”はとても重要です。
特に、発達段階で感覚の偏りや不器用さが見られるお子さまには、「楽しさ」を通じて感覚のバランスを整えるアプローチが効果的です。
今回のゼリーづくりでは、以下のような多面的な効果をねらいました:
- 手で触ることによる触覚刺激
- 色の変化をじっくり観察することで視覚認知力の育成
- スプーンで混ぜる、型に流し込むといった動作による巧緻性の向上
- 「どうなるんだろう?」という予測→観察→結果の思考プロセス
- 固まったゼリーを見て「できた!」と感じる成功体験
私たちスタッフは、子どもたちが“安心して失敗できる”、“思いきり楽しめる”環境を大切にしています。
今回の活動も、一人ひとりの「やってみたい」「見てほしい」といった気持ちを受け止めながら、個々の発達段階に合わせて丁寧に関わることを意識しました。
ゼリー作りの流れと、子どもたちの関わり
材料を混ぜて、感覚を刺激!
活動のはじまりは、材料の準備と混ぜる工程から。
今回は、紫芋パウダー・レモン果汁・砂糖・水を使って、色と味の変化を楽しむゼリーづくりに挑戦しました。
主に低学年~中学年の子どもたちがこの工程を担当し、それぞれの材料をスプーンや泡立て器で丁寧に混ぜていきます。
最初は淡い紫色だった液体に、レモン果汁を少しずつ加えると…目の前でじわじわと色が変わっていく――この瞬間、子どもたちの目が一気に輝きました。
「うわ、ピンクになってきた!」「もっと混ぜていい?」
「この匂い、なんかすっぱい」「手についた〜!」と、手を動かしながらも口々に気づきや感想を話してくれる姿がとても印象的でした。
混ぜるという単純な動作の中にも、「見る」「触る」「匂う」「考える」といった多くの感覚が詰まっており、
子どもたちは自然と感覚統合の力を育んでいるのです。
スタッフは一人ひとりの表情や反応を丁寧に観察しながら、「よく混ぜられてるね」「どんな色になってきた?」と声かけをして関心や意欲を引き出していきました。
高学年の児童は“調理リーダー”に!
活動の中盤、高学年の児童たちは“少し大人な”工程に挑戦しました。
それが、鍋を使って棒寒天を溶かす作業です。
火を扱うため、安全面に十分配慮しながら、スタッフと一緒に鍋の前に立ちました。
寒天の棒をちぎって水に入れ、火にかけながらゆっくりかき混ぜる作業。
透明だった水が次第にトロトロとした質感に変わっていく様子を、真剣な表情で見つめる子どもたち。
「もう溶けてる?」「泡が出てきたよ」「ちょっと熱いから気をつけないとね」
そうした声を掛け合いながら、調理のリーダーとしての責任感と達成感を感じていたようです。
スタッフがサポートしつつも、子どもたち自身が主導して進められたことは、大きな自信につながったはずです。
また、このような“少しハードルの高い作業”に挑戦することで、自立や実生活に役立つスキルも育まれていきます。
化学反応の瞬間に「すごい!」の声
すべての材料が混ざり、寒天液も溶けたら、いよいよ「魔法の時間」が始まります。
レモン果汁を加えると、紫芋パウダーのアントシアニンと反応し、液体の色が鮮やかに変化します。
「うわー!なんでピンクになるの!?」「さっきと全然ちがう!」
「これは理科やな!」「もう一回やりたい!」と、子どもたちは大興奮。
この化学反応はまさに“目に見える実験”。
難しい言葉は使わなくても、「自分の手で変化を起こす」体験は、子どもたちの探求心をくすぐります。
スタッフは「これはアントシアニンっていう色素の反応なんだよ」と優しく説明しながら、
子どもたちが“楽しい”と感じる中に、学びの芽が芽生えるよう意識して関わっていきました。
冷やして固めたあとは…みんなで「いただきます!」
仕上げは型に流し込み、冷やして固める工程。
時間を置いて、固まったゼリーをそっと型から外し、小皿に並べていくと、そこにはカラフルで美しいゼリーの数々が完成していました。
「わぁ、きれい!」「本当に固まった〜」「ぷるぷるや!」
その表情は、作品を仕上げたアーティストのように、どこか誇らしげ。
そして、いよいよ試食タイム。
「つめたくて気持ちいい〜」「おいしい!」「ちょっとすっぱいけど、それがいい!」と、口いっぱいに頬張る子、じっくり味わう子、
それぞれのペースで“自分で作ったものを味わう”という喜びをかみしめていました。
自分で作ったからこそ味わえるおいしさと達成感。
この最後の一口が、活動の締めくくりとして、子どもたちの心にしっかりと残ったことでしょう。
活動を通して見えた、子どもたちの成長
今回の「色が変わるゼリー作り」は、単なるおやつ作りや調理体験ではなく、子どもたちの内面の変化や成長のきっかけがたくさん詰まった、非常に価値のある活動となりました。
まず大きなポイントとして、年齢や発達段階に応じた役割分担が功を奏しました。
低学年の児童には混ぜる・型に流すといった工程を、
高学年の児童には棒寒天を鍋で溶かすなど少し高度な工程を任せることで、
それぞれが「自分の力でできた」「みんなの役に立てた」と感じられる場面がたくさん生まれました。
このような“任される経験”は、自己効力感=自分はできるという感覚を育てるうえで非常に大切です。
特に発達に特性のある子どもたちにとって、「やらせてもらえた」「うまくいった」という実感は、自己肯定感を高めるきっかけになります。
また、色が変化する様子を目の前で観察し、手を動かしながらその理由に興味をもつ姿も多く見られました。
「なんで色が変わるの?」「さっきと違う色になった!」という声に対して、スタッフが簡単な化学的な説明をすると、「もっとやりたい!」という反応も。
こうした“実体験を通じた学び”は、教科としての「理科」よりもずっと心に残りやすく、子どもたちの知的好奇心を自然に育ててくれます。
さらに、火を使うというちょっと“特別な工程”では、緊張しながらも慎重に、スタッフとともに作業を進める子どもたちの姿がありました。
「熱いから気をつけよう」「混ぜ方が難しいな」と、自分の手で扱うからこそ感じる責任と集中力。
これは、安全意識をもった行動や、生活スキルとしての“調理経験”にもつながっていきます。
“できること”が少しずつ増える経験は、自立への大切なステップになります。
そして忘れてはならないのが、仲間との関わりと達成感の共有です。
ゼリーが完成したとき、周りの子と見せ合ったり、「それキレイやな〜」「一緒に食べよう」と声を掛け合う姿も多く見られました。
一人ひとりが違う色、違う形のゼリーをつくっているのに、「どれも素敵」「全部成功だね」と認め合うやり取りは、社会性や共感力を育む貴重な場面でもありました。
この活動には、「感じる・考える・関わる・味わう」という多面的な“育ち”のエッセンスが散りばめられており、まさに“楽しく学ぶ”療育の時間だったと感じています。
子どもたちにとっても、「またやりたい」「次は何色になるかな?」という声が聞かれるなど、活動後の余韻も大きな収穫でした。
ており、まさに“楽しく学ぶ”療育の時間となりました。
見て・触れて・感じて学ぶ療育を
運動療育型児童デイぽぷらの樹東住吉では、子どもたちが主体となって「体験」を通じた学びができるよう、季節や興味に合わせた活動を積極的に取り入れています。
感覚統合、認知機能の発達、社会性の育成など、それぞれの子のペースに合わせて無理なく支援を行っています。
ご見学・体験利用、随時受付中です✨
運動療育型児童デイぽぷらの樹東住吉 では、「色が変わるゼリー作り」のような科学的・感覚的な体験活動も取り入れながら、お子さまの可能性を広げる支援を行っています。
お問い合わせ・ご見学はこちら
お電話でのお問い合わせ: 06‑6773‑9583
ウェブからのお問い合わせ: お問い合わせフォームはこちら
お気軽にご連絡ください。スタッフ一同、お待ちしております!😊