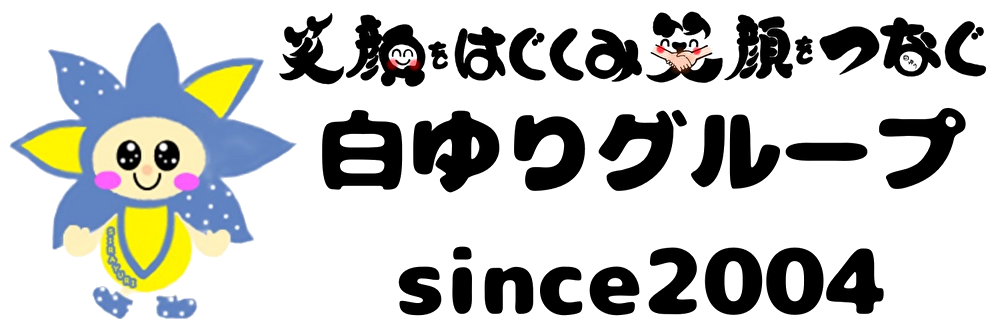「怖い」を乗り越えて。「やってみたい!」があふれたとびばこ活動の様子【ぽぷらの樹東住吉】

ぽぷらの樹東住吉で “とびばこチャレンジ” を行いました 🕊️
子どもたちにとって「できた!」という小さな成功体験は、何よりの自信につながります。特に、初めて挑戦することや、少し難しい課題に取り組む経験は、成長の大きなステップになりますよね。
運動療育型児童デイ ぽぷらの樹東住吉では、日々の活動の中で「挑戦」と「達成」を大切にしています。その一環として、先日取り組んだのが とびばこ運動。跳び箱は、ただ跳ぶだけの遊びに見えるかもしれませんが、実は子どもたちの身体能力や心の成長を引き出す要素がぎゅっと詰まった、奥の深い運動遊びなんです。

今回は、初めて跳び箱に触れる子も含めて、1段からスタートし、少しずつ段階を踏みながら最終的には6段への挑戦にチャレンジしました。それぞれの子が「ちょっとがんばれば届くかも」という高さを目指し、失敗と成功を繰り返しながら、目を輝かせて取り組む姿がとても印象的でした。
「怖いけどやってみたい」「できたからもう1回跳びたい」――そんな気持ちがあふれる、とてもエネルギーに満ちた時間となりました。
なぜ「とびばこ」活動を取り入れるのか?🧠💪
「跳び箱」と聞くと、学校の体育の授業を思い出される方も多いかもしれません。ですが、実はこの跳び箱運動は、単に“跳ぶ”という運動だけにとどまらず、子どもの成長に欠かせないさまざまな力を育む教材として注目されています。
ぽぷらの樹東住吉では、運動療育の一環としてこの「とびばこチャレンジ」を導入しました。その理由には、次のような支援的な意図があります。
✨ 全身の筋力とコントロール力を育てる
とびばこ運動では、脚力・跳躍力・腕の支持力・体幹の安定など、体全体を使った運動が求められます。踏切の瞬間に力を入れ、空中姿勢を保ち、着地でバランスを取る…これらすべてが連動することで、運動能力全般の向上につながります。
また、身体の動きを細かく調整する能力(いわゆる「ボディイメージ」の発達)にも良い影響を与えるため、日常生活での動作(階段を昇る、椅子に座るなど)にも良い変化が現れやすくなります。
🧩 思考力と“段取り力”を育てる「動作の計画性」
跳び箱に向かうとき、子どもたちは「どのくらいのスピードで走るか」「どこで踏み切るか」「どのタイミングで手をつくか」「どうやって足を開くか」「着地はどうするか」といった、一連の流れを頭の中で組み立てながら動きます。
これは「動作の見通しを立てる力」「順序立てて行動する力」=動作計画力の発達に大きく関わってきます。とびばこ活動を通して、遊びの中で自然と“考えて動く”力を養うことができるのです。
💬 不安を乗り越える勇気と挑戦する気持ち
跳び箱に初めて挑戦する時、多くの子が「怖い」「できるかな」といった不安な気持ちを抱えます。しかし、1段からスタートして徐々に高さを上げることで、「できた!」という成功体験を積み重ねることができます。
この体験は、自己肯定感の向上や、新しいことにもチャレンジしてみようとする前向きな気持ちの育成につながります。とびばこは「跳ぶ運動」であると同時に、「心を育てる運動」でもあるのです。
👭 仲間と一緒に取り組む集団活動の意義
ぽぷらの樹東住吉では、個別支援と並行して、小グループでの集団活動にも力を入れています。とびばこ活動でも、「お友達が跳ぶのを見て応援する」「他の子のチャレンジに刺激を受ける」「順番を待つ」といった社会性のトレーニングが自然と含まれています。
周囲からの応援が力になったり、他者の挑戦に触れることで「自分もやってみよう」という気持ちが芽生えたり…。一人ひとりの挑戦が、他の子の成長にもつながっていく。そんな“相互作用”が生まれる貴重な場面です。
このように、「とびばこ」は単なる運動遊びではなく、心と身体と社会性の3つをバランスよく育む総合的な療育プログラムなのです。
ぽぷらの樹東住吉でも、段階的な高さ設定や十分な安全対策を講じながら、子どもたちが「やってみたい」「できた!」と心から思える経験を積み重ねています。
実際の流れ:1段 → 6段へステップアップ
以下は、ぽぷらの樹東住吉で実施したとびばこ活動の流れと、そのときの子どもたちの様子です。
| 段数 | 主なねらい | 支援の工夫・補助 | 子どもたちの反応 |
|---|---|---|---|
| 1段 | 跳び越える基本動作の感覚をつかむ | 跳び箱に慣れるように低めでチャレンジ/手をつく位置を補助 | 「はずかしい」「できるかな?」と緊張しながらも挑戦 |
| 2~3段 | 少し高さを加えて動作を定着させる | 跳び越す感覚を練習 → スタッフ補助(片手補助など) | より力を込めて踏み切る様子、成功すると笑顔が出る |
| 4段 | 空中での操作を意識する | 軽く声かけ、タイミング指導、段差への段階的慣れ | 成功率が上がり、「もう一回!」と意欲が出る |
| 5段 | 体全体の連動を意識 | 着地の足位置や姿勢を整える指導を強化 | 成功できたときの歓声と拍手が起こる |
| 6段 | 最終の目標—踏み切り→開脚→着地の総合動作 | 安全対策を最大にし、補助やマットを活用 | 達成した子どもには大きな自信が生まれる |
このように、段階を上げるペースは子どもたちに合わせて調整し、無理なく「できた」を少しずつ積み重ねていきます。
たとえば、ある子が 3段で止まっていた段階から、スタッフの励ましと補助で 4 → 5 → 6段とクリアに向かう姿も見られました。挑戦する姿勢や、仲間の姿に刺激を受けてトライする様子が印象的でした。
成果と気づき ✨
今回の「とびばこチャレンジ」を通して、子どもたちの心と体、そして関わり合いの中にたくさんの変化が見られました。ここでは、その中でも特に印象的だった気づきや成長の様子をご紹介します。
✅ 小さな成功体験が「自分はできる」という自信に変わる
はじめは跳び箱の前に立つだけで表情がこわばっていた子どもが、「1段跳べた!」という達成の瞬間を経験すると、みるみるうちに自信を深めていきました。
特に印象的だったのは、普段あまり自己主張をしないお子さんが、2段目を跳んだあとに「次、3段に挑戦してみたい」と自ら声を上げてくれた場面です。こうした行動の変化は、自己肯定感の芽生えであり、私たち支援者にとっても何より嬉しい瞬間でした。
成功体験を通じて「自分もできる」「やってみたい」と思える力は、運動だけでなく学習や人間関係にも良い影響を及ぼします。
✅ 仲間の存在が「挑戦する力」になる
とびばこ活動では、単に跳ぶ技術だけでなく、他者との関わりの中で育まれる力も大きな成果です。
「がんばって!」「あとちょっと!」「○○ちゃんすごいね!」といった子ども同士の声かけが自然と生まれ、お互いを認め合う温かい空気が広がりました。なかには、最初は跳べなかった子が、友だちの「一緒にやろう!」という励ましに後押しされて、挑戦に踏み出せたという場面もありました。
他の子の挑戦する姿に刺激を受けたり、友だちと一緒に「次は何段いけるかな?」と競い合う姿は、集団活動だからこそ得られる大きな学びです。
✅ 安心できる関係性がチャレンジを支える
子どもたちが安心して挑戦できる背景には、スタッフとの信頼関係が欠かせません。
「怖くないよ、見ててね」「ここで手をつくと上手くいくよ」といった丁寧な声かけや、手を添えて補助しながらの挑戦が、子どもたちの不安を和らげ、成功への一歩を支えました。
また、跳ぶことができなかった時にも「挑戦してみたことがすごいよ」「また今度やってみようね」と過程をしっかりと認める関わりが、子どもたちの安心感と次への意欲につながっていると感じます。
✅ 「できた!」の次に生まれる、新たな意欲
中には6段まで跳べたお子さんもおり、挑戦を終えたあとに「もっと高いのある?」「次は7段やってみたい!」と目を輝かせて話してくれた子もいました。
こうした言葉からも分かるように、一つの成功体験が新たな挑戦への扉を開くことがあります。とびばこは、単に技術の習得だけではなく、「次に進みたい」「もっと上を目指したい」という自己成長欲求を引き出す活動でもあるのです。
また、別の子は「今度は〇〇ちゃんも一緒にやろうって言ってみる」と言ってくれました。他者との関わり方にまで良い影響が広がっていることに、私たちも驚かされました。
このように「とびばこチャレンジ」は、子どもたちにとって心と身体の成長を支えるとても貴重な活動になっています。
まとめ
とびばこは、ただ体を動かす遊びではなく、力・バランス・タイミング・挑戦心を育む総合的な運動です。ぽぷらの樹東住吉では、子どもたち一人ひとりのペースに寄り添いながら、無理なくステップアップできる支援を心がけています。
次回は、「とび箱+遊び要素」「トランポリン連結とび箱」など、バリエーションを加えた運動あそびにチャレンジしたいと考えています。
まずはお気軽にご相談ください!
運動療育型児童デイ ぽぷらの樹東住吉では、とびばこ活動をはじめ様々な運動プログラムを通じて、子どもたちが「できた!」という体験を積み重ねていく支援を行っています。
お問い合わせ・ご見学はこちら
お電話でのお問い合わせ: 06‑6773‑9583
ウェブからのお問い合わせ: お問い合わせフォームはこちら
お気軽にご連絡ください。スタッフ一同、お待ちしております! 😊